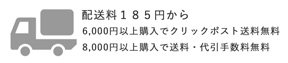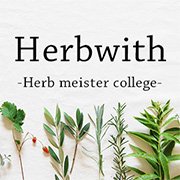ハーブと暮らしnote
HMCフィトテラピー通信 〜温活と胃腸ケア〜
 Date:2025.1.29
Date:2025.1.29
Category:ハーブレッスン
Writer:佐藤
HMCフィトテラピー通信では、こころとからだにまつわるテーマを毎月設け、ハーブや精油を用いた日々のケアや過ごし方についてお伝えしていきます。
暮らしの中にフィトテラピーを取り入れて、植物のある暮らしをより多くの方に愛しんでいただけるようご提案していきます。
********
1月のテーマは「温活と胃腸ケア」について。
「身体が冷えるのよね。」「手先や足先が冷たくて。」「太ももの裏を触ったら冷たくてびっくりした!」など、日常の会話で冷えの症状が話題に上ることがよくあるかと思います。
冬だけの話かと思いきや、季節問わず話題になっている気がします。
ごく身近にある不調のため、深刻に受け止めていないかもしれませんが、冷えが引き金になる不調はたくさんあります。
肌トラブルや下痢と便秘、肩こりや腰痛はもちろんのこと、月経痛や月経不順などの婦人科系の疾患など挙げればキリがありません。
その中でも今回は冷えと胃腸の働きの関係に注目しましょう。
一見関係なさそうだけど大いに関係ある温活と胃腸ケアのお話。
原因を探り、ご自身に合った“温活”をしましょう。
まずは何となく使っている「身体が冷える」状態とは何なのかみていきましょう。
「冷えていない」状態は、「温かい血液が身体の隅々まで滞りなく流れていること」とここでは定義付けたいと思います。
成人の全身の血管は概ね地球2周半(約10万km)の長さと言われており、毛細血管はそのうちの約95%を占め、隙間なく網目状に全身に張り巡っています。
血液は、動脈で酸素や栄養など必要なものを運んで、静脈で二酸化炭素や老廃物など不要な物を回収する働きがありますが、熱を運んで体温を調整する働きもあります。
このことから、身体の隅々まで張り巡る毛細血管に血液が滞りなく流れているかが冷え対策に繋がるのです。
私たちが寒いと思うとき、自律神経が体温調節をするように指令を出します。
そして皮膚から体内の熱が出ていくのを防ぐために毛細血管が収縮します。
サラサラと隅々まで流れているべき血液が寒さで滞りが起こり更に巡りが悪くなり、冷えからくる症状となって現われるのです。
筋肉が収縮するときに発生するエネルギーが熱の発生源となり、体温を維持する働きをしています。
特に女性は男性よりも筋肉がつきにくく、熱源量が少なく冷えやすくなっています。
働いている女性の実に6割以上が冷えの諸症状に悩んでいるというデータもあるそうです。
筋肉量が落ちないように簡単な筋トレを長期的に地道に続けることも温活の一つ。
そして同じ理由で痩せすぎも筋肉量の不足で冷えの原因となります。
もちろん皮下脂肪は一度冷えると温まりづらいと言われていますので太りすぎもよくありません。
ご自身のBMIを知っておくことも温活に繋がります。(BMI18.5未満が痩せすぎとされています。)
デスクワークで一日座っている方も、たまに立ち上がってスクワットをするなど、ふくらはぎに筋肉をつけてしっかり心臓に血液を戻して巡りの良い身体を作りましょう。
また、自律神経の乱れも冷え性の原因の一つです。
季節問わず体温がほぼ保たれているのは自律神経(交感神経と副交感神経)の働きでバランスをとっているから。
・季節の変わり目
・屋内と屋外での急激な温度差
・ストレスや不規則な生活
・偏った食生活
などが自律神経のバランスの乱れの原因となり、体温調節が一定に保たれなくなってしまいます。
それがひいては冷えの症状に繋がるので、
・規則正しい生活を心掛ける
・シャワーだけでなくバスタブに浸かって温めながらリラックスする
・自分だけのストレス解消法を持っておく
など日頃からできる範囲でケアを心がけましょう。
白砂糖や白米、小麦製品などの精製された食品も身体を冷やすと言われています。
冷えが気になる時はいつもより控えてみると良いかもしれません。
お菓子を食べたくなったら、美味しいハーブティーに置き換えてみるのも一つのアイディアです。
<おすすめブレンド>
■ Beauty & Cleanse
ステビアの天然の甘さとハイビスカスの酸味が絶妙なバランスの人
血流促進効果もあり一石二鳥!
■ Herb De Chai
身体を芯からポカポカ。スパイスたっぷりノンカフェインのチャイ
口寂しい時はミルクを入れて満足感アップ!
冷えによって起こる不調がたくさんあるのは前途の通りですが、胃腸との関係はどうでしょうか。
「内寒」という言葉があります。
寒さによって陽気が不足し、体内の機能が低下することをいいます。
主に食欲不振や消化不良など胃腸に症状が出やすく、
・お腹を触ると冷たい
・疲れやすい
・肩こりや腰痛がある
場合は、
・甘い物や加工食品をできるだけ控える
・身体を温める性質のある食べ物や味噌などの発酵食品を積極的に摂る
・身体を温めエネルギーを補う
ようにしましょう。
冷えた状態から温めるには相当のエネルギーが必要です。
暖かい服装を心掛けて無駄な消耗をしないようにしましょう。
4首(首、手首、足首、くびれ(腰))を冷やさないようにするのもポイントです。
また、消化には蠕動運動が欠かせないので、腹筋の働きも大切になります。
筋肉は熱の産生にも関わっていましたね。その中でも腹筋は消化のためにも必要なのです。
このことを理解するのにとても分かりやすいと思ったのは、アーユルヴェーダの大切な概念であるアグニ(サンスクリット語で消化のための炎という意味)が正常に働いていることという考え方です。
このアグニがあるからこそ、食べた物は消化され身体を作る元の栄養となるのです。
冷えが強くなると消化の火は消えかかり消化不良を起こし未消化物が体内に残り不調を招くのです。
消化の火が強すぎてもいけません。
適切な炎であることで、食べた物は栄養となって身体を作るのです。
(注1)
東洋医学の視点からも温活と胃腸ケアについてみていきましょう。
五臓六腑の全てのバランスが整っていることが大切ですが、冷えのタイプを大きく
「気血不足」
「血行不良」
「陽気不足」
に分けて考えた時に、この三つの中で胃腸と関連深いのは「気血不足」になります。
身体のエネルギーであり生命の源である「気」と、全身の組織に栄養を運ぶ「血(けつ)」。
気の統率により血を巡らせることができ、血は気を載せて全身を巡りエネルギーを生み出します。
この気と血は胃腸で消化吸収され作られます。
全身に血が巡り、気が充実した毎日を送るためにも胃腸の働きは大切で、冷たい物は避けて胃腸の働きを守ることが重要になります。
五臓六腑での消化器官は「脾」と「胃」に当たります。
脾の働きは飲食物を消化し、栄養素を吸収して身体に必要な気血水を作り出します。
食べた物を栄養に変え全身に押し上げて運んで循環させます。
押し上げる力にも熱(筋肉)が必要で、バランスが崩れると食欲が減退しお腹の張りなどの症状が出ます。
脾が弱っていると身体に良い物を摂っても全身に気血が充実しないのです。
胃の働きは脾のコントロールの元で食べ物を消化し、小腸へ降ろす働きをしています。
この初期消化の働きは生命活動を維持するのにとても重要です。
たくさん食べてもしっかり胃で消化されないと気血は満たされず、栄養が身体を巡らないと考えられます。
食べた物をしっかり消化できることで身体は出来ているということです。
食べ過ぎなどで胃が熱を持ちすぎてしまうと胃の気が上がり、陰陽のバランスが崩れて吐き気や嘔吐などの症状が出ます。
この脾胃は、冷やし過ぎないことが第一です。
負担をかけないように体温以上の温かい物を食べて、初期消化の負担にならないように腹八分目を目指しましょう。
胃腸ケアに関係の深い臓腑「脾」や「胃」、「気」「血」についての詳細は、HMCのオンライン講座「陰陽五行フィトテラピー講座」で詳しく説明しています。
もっと知りたい!という方はぜひこちらもあわせてご覧ください。
では、フィトテラピーでは温活と胃腸をどのようにサポートできるでしょうか。
「食べ物」と「香り」と「ハーブティー」の観点からおすすめしていきます。
<食べ物>
お腹を内側から温める「温裏」の食材を摂ることが冷え性対策となります。
スパイス全般や、ニラ、乾姜(蒸してから干したショウガ)や白ネギ、ヨモギ、海老や鮭も温めてくれます。
またお肉では羊肉や鹿肉が温活にはおすすめ。
また、味噌などの発酵食品もお腹から温めてくれて、腸活にもつながるのでこまめに摂るとよいでしょう。
<精油>
温活へのおすすめの精油は、マージョラム・スイートです。
甘さとスパイシーさを兼ね備え、血流だけでなくリンパの流れも促進します。
冷えからくる肩こりや消化器系の不調にも温めながら老廃物を流します。優しくマッサージしてくださいね。
■ マージョラム・スイート<精油>
<ハーブティー>
ハーブティーの飲用を習慣づけることも温活と胃腸ケアの一助となります。
■ ジンジャー
身体を温めてくれるハーブのファーストチョイス!
身体を温めることはもちろん、温めることによって胃腸の働きを正常に保ち消化を促進します。
少し贅沢に手浴や足浴に入れても末端から温まります。
■ シナモン
とても身体を温めるハーブです。
足だけ冷えるなどのお悩みに、巡りを良くしながら温める働きもあります。
冷えからくる風邪や関節炎、下痢や生理痛など冷えが強いときにポイントで使うのもおすすめです。
常に冷えを感じている方はパウダーなどを使ってこまめに摂取すると良いでしょう。
ブレンドハーブティーにすると1杯で複数のハーブが摂取でき、飲みやすくハーブ同士の相乗効果も期待できます。
■ 土調茶
季節の変わり目である土用の時季は胃腸をケアしたい時季でもあります。
温かいハーブティーを飲んでのんびり過ごしましょう。
■ After a meal
食後の消化を促してくれるブレンドです。
温めはもちろん、食べ過ぎてしまったときにも。
■ Relax & Warm
季節を問わず冷えてしまうあなたにおすすめのブレンドです。ジャーマンカモミールの優しい味が冷えによって滞った心身を癒してくれます。
「冷え」の原因や引き起こす不調は数えきれないほどあり、ここでは書ききれないほどです。
ということは、身体が冷えることは身体からの不調のサインかもしれません。
冷えは万病のもとという言葉もあるくらいです。
「冷え」が身近な単語なだけにちょっとした不調として見逃しがちです。
たかが冷え性と侮らず未病の段階で早めの対策を心掛けましょう。
まれに甲状腺機能異常や膠原病などが冷えの原因になっていることもあります。
気になる方は一度受診されることをおすすめします。